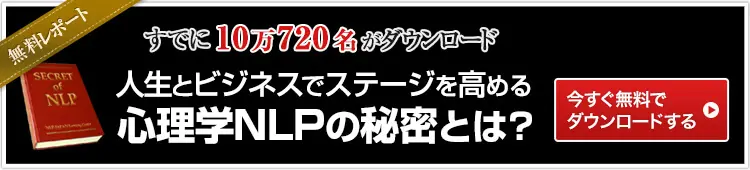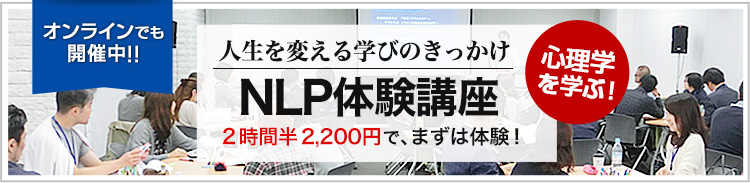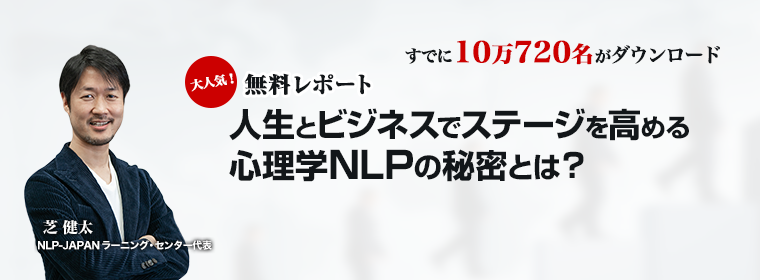看護師に求められるスキルは多種多様。
その中でも「コミュニケーションスキル」は、
患者さんやそのご家族との間だけではなく、
医師をはじめとした他職種との連携を密に行う場面でも
必須のスキルです。
一方で、現場で働く看護師のなかには、
-
「患者さんと信頼関係を築きにくい」
-
「忙しくてゆっくり話をする時間がない」
-
「スタッフが忙しく、ピリピリしていて
コミュニケーションを取るのが怖い」
これらの悩みを抱えている方も多いかもしれません。
また、目の前の患者さんに真摯に向き合い、
救いたいと尽力し続ける看護師は、
優先順位を『自分<患者さん』とする傾向が高いため
自分自身や自分の人生を疎かにしていることに
気づかない方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、そうした方に向けて
心理学NLPを使った看護コミュニケーションの取り方をご紹介します。
心理学NLPは、看護の分野を超えて人とのコミュニケーションに役立つことはもちろんですが、
「自分の内面を整えること」にも役立ちます。
ただのコミュニケーションスキルではなく「自分の内面を整える」ことも可能にする、
NLPにもご興味がある方は、第4章で詳しくご紹介しますので、ぜひご覧ください。
目次
1.看護におけるコミュニケーションと信頼関係の重要性
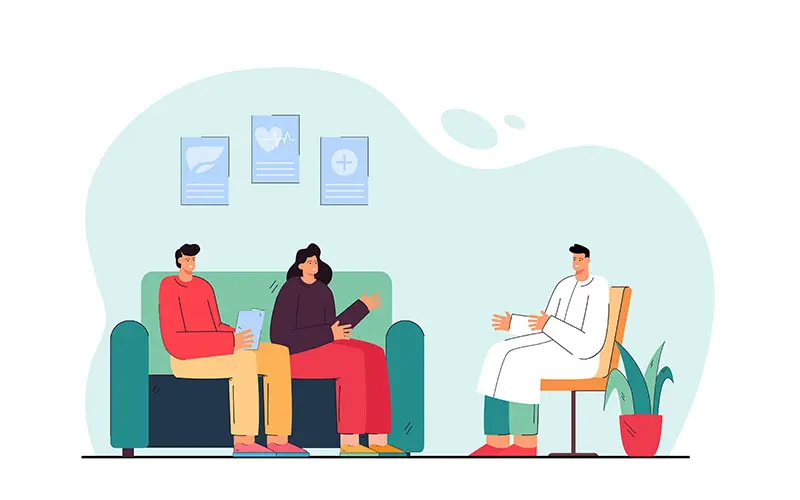
仕事ができる看護師のイメージは、採血や注射など看護技術に長けていると感じる方が多いでしょう。
しかし実際のところ、仕事ができる看護師の共通点として、コミュニケーション能力が長けていることが挙げられます。
看護師は「人」を相手にする職業であり、特に患者さんは、病院での治療中、病気への不安や治療への葛藤を抱えていることが大半です。
気持ちを理解して、寄り添った看護をするためにも、コミュニケーションスキルは必要不可欠です。
また、看護の場においてコミュニケーションと同等に重要とされているのが、「信頼関係」です。
患者さんやそのご家族との信頼関係があることで、患者さん中心の良質なケアを提供することができますし、
医師やチームとの信頼関係があることで、報告・連絡・相談がスムーズになり、安全で患者さんの希望に沿ったサポートをすることができます。
ここでは、看護師が日常的に接する3つのパターンにおける信頼関係の重要性をお伝えします。
- 患者さんとの信頼関係
- ご家族との信頼関係
- 医師・看護師との信頼関係
1-1.患者さんとの信頼関係

患者さんの多くは、不安な気持ちを抱えて病院にやってきます。
その不安は、病気そのものに対しての不安や治療、治療に伴う経済的な面など様々です。
そういった不安を抱える患者さんは、精神的にも感情的にもマイナスの状態にあることが多く、それにより、治療やリハビリなどに身が入らないということも少なくありません。
日本看護協会は、患者さんとご家族との信頼関係の重要性を下記のように明記しています。
看護職と患者・ご家族が相互に「信頼」する関係を構築することが、看護を提供する前提である。
また、信頼関係に基づいた患者・ご家族の協力が不可欠であり、より質の高い保健・医療・福祉を作り上げることにつながる。
いかに患者さんとコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことができるかが、患者さん中心の医療を提供するための鍵となり、後々の看護にも大きな影響を与えます。
患者さんと信頼関係を築くことが、とても大切なことなのがわかりますね。
1-2.ご家族との信頼関係
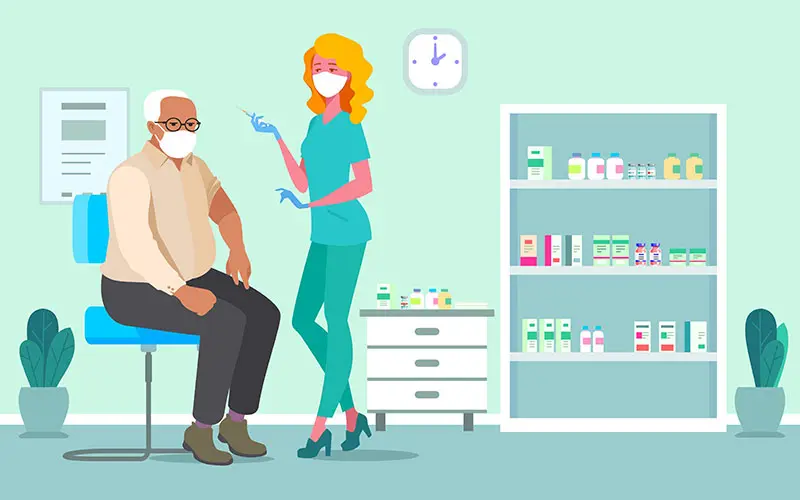
医療現場において患者さんとのコミュニケーションはもちろんのこと、患者さんのご家族とのコミュニケーションも同じくらい大切です。
ご家族は、ご家族の誰かが病気になることで、患者さん同様に、不安や緊張を抱え、相当なストレスを抱えてしまいます。
そのため看護師は、患者さんのみをケアの対象とするのではなく、患者さんのご家族もケアの対象とする必要があります。
積極的にご家族全体を支援することで、ご家族との信頼関係を築き、協力して患者さんを支えることができます。
また、ご家族との信頼関係を築けていると、治療に抵抗を示す患者さんへの説得もしやすくなります。
私の祖父もそのような患者の一人で、脳梗塞で入院した際に、治療やリハビリに反抗的で、暴れるようなこともありました。
そうした時に、私たちご家族が真っ先に相談した相手は、医師ではなく、祖父を担当してくれていた看護師さんでした。
その看護師さんが、日頃の祖父の言動を観察、共有してくれたおかげで、解決策を練り、リハビリに前向きに取り組んでもらえるようになりました。
まだ小学生だった私も、その看護師さんがいてくれてよかったと思った出来事でした。
今振り返ると、私たちご家族と看護師さんとの間に信頼関係が築けていたことが、祖父の行動の変化に大きく繋がったと感じています。
1-3.医師・看護師との信頼関係

患者さんにより良い医療を提供するためには、医師や看護師、薬剤師、栄養士など様々な専門職との関わりがとても重要です。
患者さんと関わる他職種の中で、看護師にとって最も関わりが強いのが、医師と看護師同士でしょう。
医師の指示を確実に行う必要がある時は、何度も看護師に確認の電話をする医師もいます。
このような場合に、信頼関係があると「間違いのないように、確認をしてくれている」「ありがたい」と捉えることができる一方で、
信頼関係がない場合は、もしかすると
「信頼されていない」「うっとうしい」といった感情が生まれてしまうかもしれません。
これらの不満や不安が募ってしまうと、ほかの治療を行っていても医師からの指示を話半分で聞いてしまったり、うんざりしてしまったりと余計に仕事に支障が生じる危険があります。
医師そして看護師同士のコミュニケーションが良好だと、信頼関係が生まれ、円満なチームワークにも繋がり、最終的に患者さんの満足度も高くなります。
『患者さんに早くよくなってもらいたい』という共通の目標に向かって医師や仲間と切磋琢磨しあえれば、看護師自身の資質・技術向上につながることは間違いありません。
2.明日にでも試せるコミュニケーション&ラポールスキル
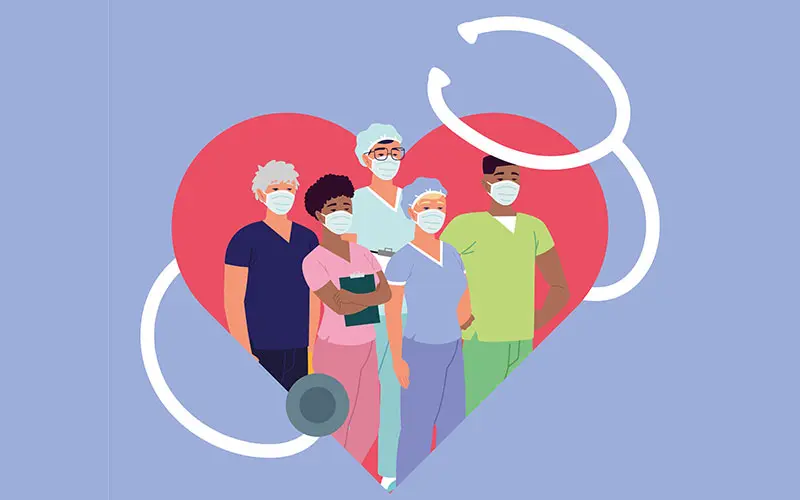
患者さん・患者さんのご家族・医師や看護師間のコミュニケーションから生まれる信頼関係の重要性をここまでお伝えしてきました。
信頼関係は、NLP用語で「ラポール」といい、質の良いコミュニケーションを目指すのであれば、ラポール形成は必要不可欠です。
ラポール形成ができると、初対面から始まる人間関係やすでに関係性が築けている人とでも、安心感や信頼感を獲得することができ、円滑なコミュニケーションを進めることができます。
とはいえ看護師は、たくさんの患者さんに対応しなくてはいけないため、「なかなか、一人一人とコミュニケーションをとる時間がないんです!」という方も多いでしょう。
時間に追われる中で、言葉のキャッチボールが少なく、作業的な対応になってしまうのか、
短いながらも思いやりが感じられるコミュニケーションがあるのかでは、患者さんとの関係性や信頼性が大きく変わってきます。
ここからは、信頼関係(ラポール)を築くためのコミュニケーションスキルを4つご紹介していきます。
看護師の方々が忙しいのは言わずもがなのことですが、忙しい合間でも以下4つのスキルを少しでも気にかけてみると、自分の言葉が相手へ冷たく伝わったり、温かく伝わるということがわかるようになります。
「そこまでコミュニケーションに時間をかけていられない」と感じる部分もあるかと思いますが、信頼関係を築く上で、大事なスキルをご紹介していますので、使える範囲でも意識してみるところから始めてみることをお勧めします。
2-1.傾聴
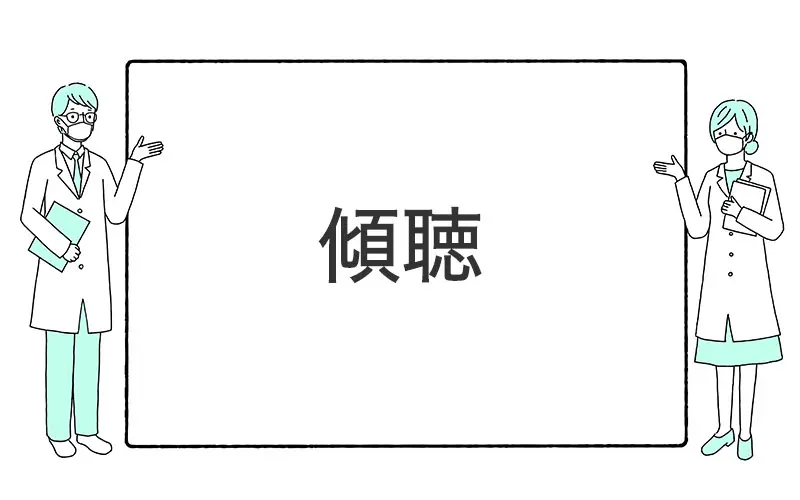
傾聴とは、相手の話を中心に聞くコミュニケーションスキルです。
相手の話を否定することなく、肯定的に理解を示し気持ちを汲み取り、共感、尊重し話を引き出す聴き方です。
傾聴力が低い場合、以下のように損をしている可能性があります。
- フォローやケアできたはずのスタッフが退職する
- 相手への理解と共感不足によって、人間関係の問題がこじれる
- 相手が必要としている変化や行動に、気づくことができない など
アメリカの心理学者カール・ロジャース博士が提唱した「積極的傾聴」には3大要素があります。
(1)共感的理解
相手の話を、相手の立場に立って、相手の気持ちに共感しながら理解しようとする。
(2)無条件の肯定的関心
相手の話を善悪の評価、好き嫌いの評価を入れずに聴く。
相手の話を否定せず、なぜそのように考えるようになったのか、その背景に肯定的な関心を持って聴く。
そのことによって、話し手は安心して話ができる。
(3)自己一致
聴き手が相手に対しても、自分に対しても真摯な態度で、話が分かりにくい時は分かりにくいことを伝え、真意を確認する。
分からないことをそのままにしておくことは、自己一致に反する。
つまり、相手が話していることを遮ったり否定したりせずに、共感し、相手がさらに話を続けやすくなるよう「真摯に聴く」ことが大切ということです。
このような話の聴き方ができるようになると、
- 「私のことをわかってくれる」
- 「あなたに話してすっきりした」
- 「私のことを大事にしてくれている。安心する」
といったポジティブな反応を得ることができ、それが信頼関係(ラポール)に繋がります。
このように、傾聴力があるかないかで信頼関係(ラポール)に大きく影響を与えています。
2-2.リフレーミング
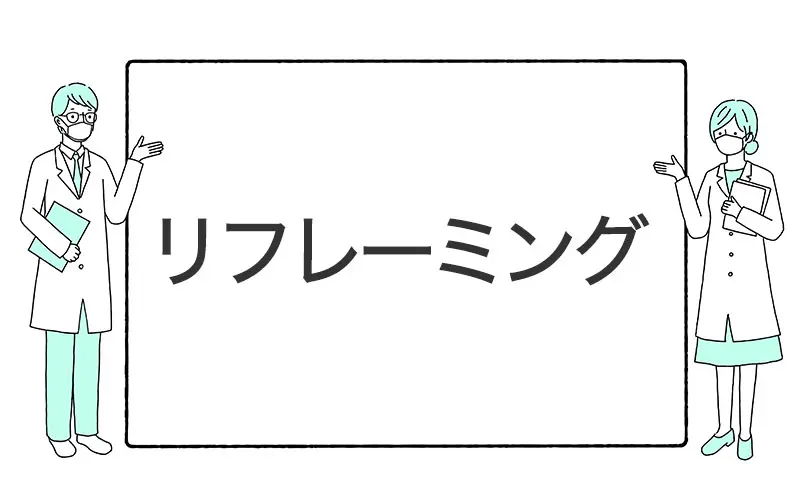
リフレーミングとは、心理的枠組み(フレーム)を組み直すことによって、人や物事への印象や意味を変化させ、新しい見方・考え方に転換すること(転換できるようになること)をいいます。
悩みや問題を抱えて落ち込んだり、行き詰まったりした状態にあるとき、
「リフレーミングによって、新たな選択肢を見いだしたり、やる気を取り戻したりできる理想的な心理状態にしていくこと」
を目的としています。
ここでは行き詰まったフレームをどのようにしてリフレーミングしていくのか。その方法を1つご紹介します。
2-2-1.言葉の定義をリフレーミングする
このリフレーミングは、言葉の定義や意味を変えて、行き詰まった状態から前に進める状態へ切り替えるための方法です。
例えば、「怒りっぽい」という言葉があります。
「些細なことで怒る」「沸点が低い」などといった意味を表しますが、一方で「感情豊か、まっすぐで素直、人間味がある、正直」という表現をすることもできる言葉です。
ですので、例えば患者さんが「なんで私が病気にならなきゃいけないの」という言葉を発したとすると、
どう言葉を返していいかわからないことも多いのではないでしょうか。
この言葉には「病気=嫌なもの、不幸」と捉えられていますので、
それをリフレーミングすると、以下のようになります。
- 「もしかすると、身体が『少し休ませてくれ』と訴えているのかもしれないですよ」
- 「このまま突っ走ったら体が壊れてしまう!」というメッセージだったんじゃないですか」
- 「無理していた身体をメンテナンスするチャンスです」
というように考え方を切り替えることで、
「病気」という言葉の定義も違った視点で捉えることができます。
一言二言の言葉の投げかけで、患者さんの気持ちがぱっと変わると、それだけで、看護師への親近感や信頼性も格段と上がります。
コミュニケーションをとるのが上手な人は、一言二言の会話で相手の心を視点を変えるリフレーミングが上手なことがほとんでです。あなたもコミュニケーションの達人を目指して、リフレーミング力を鍛えてみてはいかがでしょうか。
2-3.バックトラッキング
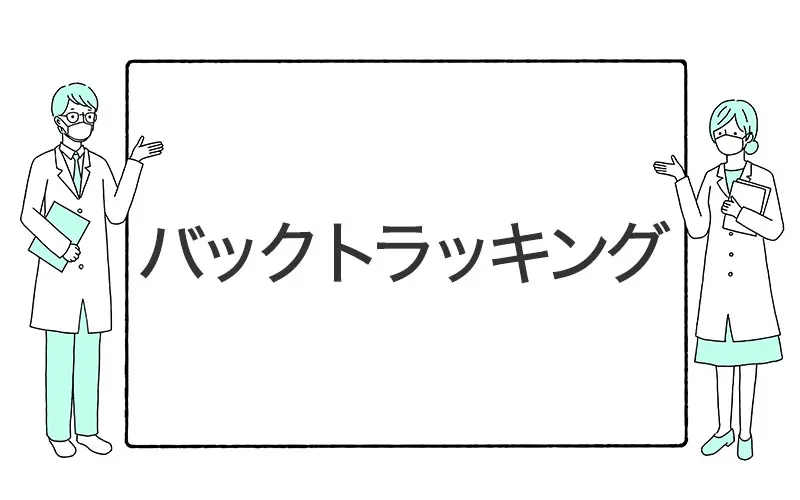
バックトラッキングとは、相手が発した言葉を繰り返して、会話を進めていく聴き方のスキルです。
オウム返しと言われることもあります。
バックトラッキングをすることで、以下のような効果を得ることができます。
- 否定や拒否といった違和感や抵抗感を緩和する
- 「自分は大切にされている」というポジティブな感覚を与えることができる
- 「自分のことを知ろうとしてくれている」と思ってもらえる
私は、祖母が病気で入院していた際に、このバックトラッキングをよく使っていました。
祖母が、昔の思い出話を聞かせてくれていた時のことです。
祖母:私の父は、宮内庁で宮様にお仕えしていたんだ。
私:ひいおじいちゃんが!?宮内庁に勤めてたの!?それも宮様に???
祖母:そうそう、そうなの。だからね。宮様からのお手紙とかもあるのよ。
私:え!?宮様からお手紙いただいたの。
という会話が進みました。
祖母はこの話をしている時、とても満足そうな表情をしていたのをよく覚えています。
このバックトラッキングとは、相手の「そうそう」「そう。そうなんだよ」という無意識の声で、
「YES」の意味を含む肯定的な言葉をたくさん生み出す会話の仕方です。
「YES」の多い会話を続けていると、
「自分の話を聴いてもらっている」という安心感
「受け入れてもらっている」という肯定感、
そして信頼感を相手に与えることができるので、
相手がオープンとなり、心を開いてくれます。
聴くことを通して、
・あなたのことを理解しようとしています
・あなたのことをもっと知りたいです
というメッセージを相手の無意識に届けるコミュニケーションスキルが、バックトラッキングです。
2-4.ペーシング
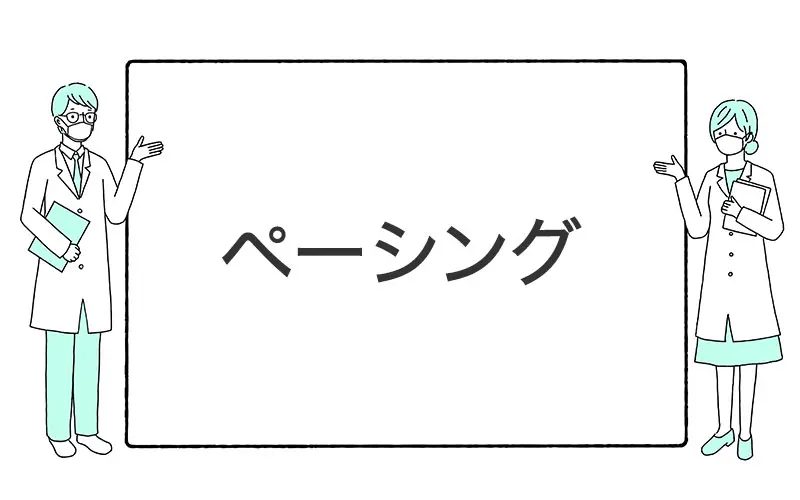
相手の言語、非言語に合わせていくこと、それがペーシングです。
例えば初めて会った人でも、同じ出身地や共通点があるとわかると親近感が湧くと思います。
他にも同じ様な境遇や趣味などが見つかると、さらに安心感や好感、親和性が高まります。
それと同じように、相手の仕草や声の調子を合わせていくこと、また相手が使っている言葉を盛り込みながら会話をしていくことで、以下のような効果を得ることができます。
- 相手の警戒心を取り除き、安心感を与えることができる
- あなたのことを大切な存在、重要な人だと認識し始める
- あなたの話や提案を受け入れてもらいやすくなる
ペーシングには、大きく分けて「ミラーリング」「マッチング」「バックトラッキング」という3つの基本スキルがあります。
ここでは、2-3で扱ったバックトラッキングは割愛し、「ミラーリング」と「マッチング」をご紹介します。
2-4-1.ミラーリング
ミラーリングとは、相手の仕草や表情を合わせていく技法です。
名前にあるように、鏡のように相手の動作や仕草を合わせていくやり方です。
具体的にお伝えしますと、
- 表情や顔の向き(頭の傾きや口角や目の開き具合、眉間など)
- 上半身や下半身の動きや角度や姿勢(背筋の伸びや腕や足を組んでいるなど)
- 呼吸(深いのか、浅いのか、肩で息をしているなど)
などの特徴を合わせていきます。
ここでお伝えしておきたいのが、ミラーリングは決して「モノマネ」ではないということです。
このミラーリングは、相手に気づかれてしまうと効果が半減どころか、逆に不快感を与えかねません。
ですので、「さりげなく相手に気づかれないようにする」、これが大切なポイントです。
常に同じ動作や仕草ではなく、時間差で合わせにいっても問題ありません。
相手を尊重する、配慮することを前提に考え、ラポールを形成するためにミラーリングをしていますので、あなたの聴きやすさではなく、相手の話しやすさを慮ることが必要です。
2-4-2.マッチング
次にご紹介するのは、「マッチング」という技法です。
マッチングとは、相手の声の調子を合わせていくというもので、具体的には下記の項目を合わせていきます。
- 声のトーン(高い、低い)
- テンポ(早い、ゆっくり)
- ボリューム(大きい、小さい)
- リズム
例をお伝えすると、このマッチングの効果がわかります。
あなたが早口で話す人だとします。
そして、相手がゆっくり話す人だとすると、話の内容ではなく、会話のテンポのズレによって、イライラしたり、違和感や嫌悪感を感じると思います。
人はそれぞれ話しやすいペースやトーンがあります。
そこに合わせられるように、日頃から自分の声の調子を理解し、早くもゆっくりとも話せる。
また、声を高くしたり、低くして話せるように日頃から意識をしておくことが重要です。
看護師が接する患者さんは特に、センシティブな心境になる方がいる一方で、関係を築くことを避ける方も多いです。
そうした方々との会話でも、マッチングを意識した声の掛け方は信頼関係(ラポール)を築くための大切な鍵となりますので、ぜひ実践してみてください。
3.対象者別の看護師に求められるコミュニケーション

看護師は、患者さんだけではなく、他職種との綿密なコミュニケーションが求められるお仕事です。
ここでは、看護師に求められる対象者別のコミュニケーションにおける大切なポイントをご紹介していきます。
3-1.患者さんやご家族とのコミュニケーション
患者さんやそのご家族に対してのコミュニケーションは、信頼関係(ラポール)の構築が大前提です。
何よりも信頼関係(ラポール)の構築を第一として、スムーズにコミュニケーションが取れる関係性を作ることに努めましょう。
そして、患者さんやそのご家族と接するにあたり、以下の項目に注意していくことをお勧めします。
- 落ち着いて話ができる雰囲気を作る
- 「話す」と「聴く」のバランスを取る
この2点を具体的にご説明していきます。
3-1-1.落ち着いて話ができる雰囲気を作る
患者さんは、医師や看護師をよく見ています。
バタバタと忙しそうにしていたり、ピリピリした雰囲気を纏っている看護師の方には、なかなか話しかけにくいものです。
会話するための雰囲気作りは、患者さんやご家族とのコミュニケーションをとる上で、重要なウエイトを占めているのです。
(1)ゆっくりと話を聞くための時間を確保すること
(2)多忙などの自己都合で、相手を不快にしないよう感情をコントロールする
(3)笑顔で安心できる話しやすい雰囲気を作る
これらを意識すると、患者さんやそのご家族は、「この人なら優しく話を聞いてくれそうだ」といった印象を受けて安心して会話することができます。
人を寄せつけないような雰囲気が出てしまっていたり、感情のコントロールがうまくいかないときには、「自分を整える」ということを行うと改善していきます。
その詳細を4章でご紹介しますので、気になる方は是非そちらもご覧ください。
3-1-2.「話す」と「聴く」のバランスを取る
患者さんとのコミュニケーションに限らず、会話とはキャッチボールのようなものです。
キャッチボールのつもりが、一方通行の会話になっていないか自分の会話を見つめてみましょう。
例えば、患者さんから相談を受けたため張り切ってアドバイスをしましたが、患者さんからの反応はイマイチだったりしていませんか?
このような会話をしていると、患者さんは一方的に意見を押し付けられた、と感じてしまう場合があります。
実践心理学NLPでは、「相手の反応は、自分のコミュニケーションの成果である」という考え方をします。
自分のコミュニケーションが相手に届いているのかをしっかりと観察、ペーシング、マッチングし、
一方通行のコミュニケーションではなく、「話す」と「聴く」のバランスが取れているかを意識しましょう。
3-2.看護師同士・医師とのコミュニケーション

次に、看護師同士・医師とのコミュケーションで求められる大切なポイントをお伝えしていきます。
看護師の中には、医師とのコミュニケーションに悩みを抱えている人も少なくないでしょう。
高校の同級生で看護師の友人は、「報告すると先生の機嫌が悪くなることがあって、萎縮してしまう人がいる」と話してくれたこともありました。
特に、看護師になりたての新人さんは、周りの医師や先輩看護師とのコミュニケーションに苦戦することが多いようです。
(1)相手の立場に立って報告する
(2)コミュニケーションを上手く取っている人を真似る
報告のタイミングや伝え方がうまくいかない!そんな時には、上記2点を是非参考にしてみて下さい。
3-2-1.相手の立場に立って報告する
医療業界の枠に留まらず、どの仕事をしていても「相手の立場に立って、わかりやすい報告をする」ことというのは、仕事におけるコミュニケーションの基本とも言えるでしょう。
医療関係者ではありませんが、会社員として働く私も上司への報告時に、上記の問いかけを意識しています。
報告もコミュニケーションの1つです。
「わかりやすく伝える」「受け取りやすく伝える」ことができれば、仕事においても人間関係においてもプラスの成果に直結します。
逆に、「わかりにくいメッセージ」は、意思疎通を妨げ、ミスに繋がります。
さらには、相手のストレスや誤解を招いてしまうことも。
わかりやすく伝えるためには、「相手がメッセージを受け取る準備ができているか」も大切です。
大事な報告をわかりやすく伝えても相手が忙しくて、報告を受け取ってもらえない場合も大いにあります。
例として、
- 「今よろしいですか?」と確認してから話す
- 目的やテーマを告げてからやりとりを始める
相手が受け取りやすい状態かどうかを確認した上で、コミュニケーションを取るようにしましょう。
相手の受け取る準備が整っていると判断できたら、今度は伝える方法を意識してみましょう。
例えば、
- 伝える内容がいくつあるのか
- 結果から伝える
- 事実と主観の区別して報告する
いきなり話の中身を伝えられても、聞き手側は何に注意して聞けば良いのか分からず混乱してしまいます。上記のポイントを意識して、会話を組み立ててみると良いかもしれません。
3-2-2.コミュニケーションを上手く取っている人を真似る
コミュニケーションが上手な人に注目してみると、その会話のコツや工夫を知ることができます。
医師や看護師とのコミュニケーションを上手にとっている人を思い浮かべてみましょう。
周りの先輩、同僚、後輩でもいいですし、身の回りにそうした人がいなかったら、ドラマや映画のキャラクターでも大丈夫です。
上手なコミュニケーションをとっている人が
- どういう言葉を使っているのか
- どういう順番で話しているのか
- 話すスピードはどれくらいか
目だけではなく、耳を傾けてよく聞き、よく観察します。
手本となる人がどんな会話をしているかに注目し、その会話の仕方を徹底的に真似することで、自分がとっていたコミュニケーションとの違いを発見することができます。
4.自分の整え方〜NLPとは〜

ここまでNLPを使ったコミュニケーションスキルをご紹介してきました。
ここでは、冒頭で、軽くお伝えしました
心理学NLPを通して「自分を整える」ことにフォーカスしていきます。
自分の内面をバランス良く整えることは、人生を長い目で見たときにとても大切です。
例えば、マイナス面を抱えた状態で相手とのコミュニケーションを取ろうとしてもうまくいかないこともありますし、
自分の人生の5年後、10年後を考えたときに、自分の内面とのコミュニケーションをとっておくことが、これからの人生を送る上でとても大切なのです。
人生を上手に生きている人の共通点として、時折人生を一度立ち止まって、自分とのコミュニケーションをとるようにしています。
看護師の中には、日頃の忙しさから優先順位を
「自分 < 患者」「自分 < 仕事」とベクトルが向いてしまっているという人も少なくありません。
そうした方に向けて、自分を整えるためにお勧めしたい方法1つをご紹介していきます。
4-1.自分の価値観に注目する
「人生時計」という言葉をご存じでしょうか?
一度の人生を24時間で考えると、今は何時なのか?がわかります。
方法は、今の年齢を3で割るだけ。
45歳であれば、「45÷3=15時」となります。
この人生時計は、あくまで想定であって確定ではありません。
ですが、人生の残り時間を実感するにはちょうど良いと思います。
自分の残り時間が、あと数時間の方もそうでない方も、自分が残りの人生で何を大切にして生きていきたいか。その価値基準を明確にしておくことはとても大切です。
なぜなら、困難な状況にあったときや、選択を迫られたときに、大切なものを失うことなく、スムーズに決断することが可能になるからです。
【やり方】
「人生で大切だと思うことは何か?」を自問してしていきます。
そして「他に、人生で大切だと思うことは何か?」を10回程度繰り返し、1枚の付箋につき1つ書き出します。
次に、大切だと思う順に、違和感がなくなるまで付箋を並びかえるということを行います。
ここでのポイントは、損得勘定や論理的に並び変えるのではなく、直感で並び替え、
頭ではなく、感覚でしっくりくるまで繰り返し並び替えることです。
このように出てきた価値観を並び替えていくと、自分が大切にしている価値観とその順番がわかってきます。
そして価値観を明確にすることで、自分が本当に大切にしたいものに気づき、それを満たした理想の人生に向かって行動していくことができます。
4-2.NLPとは
ここまでご紹介したコミュニケーションスキルは、心理学NLPを取り入れたものばかりです。
そこでここでは、NLPについて簡単に解説していきます。
NLPとは、Neuro Linguistic Programing(神経言語プログラミング)の略称で、別名「脳と心の取扱説明書」とも呼ばれている最新の心理学です。
天才たちが使う『ことばの使い方』や『ノンバーバル(非言語)の使い方』、『無意識の活用の仕方』を科学的に分析し、体系化された心理学であり言語学でもあります。
そして誰もがそれを実践し、再現できるようにしたことで、大きく発展していくことになりました。
NLPでは、以下5つの分野について学ぶことができます。
- 他者とのコミュニケーション
(人間関係、信頼関係を構築する) - 自分とのコミュニケーション
(自分の内面の整理と人生の方向性を明確にする) - トラウマやコンプレックスなど、心理的なマイナス面の解消
(結果を妨げるネガティブな足枷を解消する/軽減する) - セルフイメージの向上
(目標達成や問題解決の能力を高める/引き出す) - 健康の維持・促進
(病気に対する心理的なアプローチ)
NLPのスキルを身につけることで、自分の内面や周囲に根本的な変容をもたらすことが可能なため、
元は心理療法(セラピー)から始まったNLPでしたが、
その効果の高さから、現在では、経営者やリーダー層にも多く学ばれています。
今回ご紹介したコミュニケーションスキル以外にも、NLPのプログラムは豊富にあります。
もし、ここまで読んでいただいた方で、NLPに少しでも関心が湧いた方は、まずは10万名以上の方がダウンロードした「無料レポート」を読んでいただくか
毎回たくさんの方がご参加される、NLP体験講座や10日間の実践コースを受講してみてください。
NLP体験講座では、4-1でご紹介した「価値観の洗い出し」についても触れていきます。
ぜひ気軽にご参加なさってください。
無料レポートはこちらから。
↓
人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密
心理学NLPの体験講座はこちらから。
↓
NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中
あなたを進化させる、最先端の10日間NLP実践コースはこちらから。
↓
NLPプラクティショナー認定プレミアムコース
まとめ
いかがでしたでしょうか。
全ての看護師に向けて下記の手法を、看護コミュニケーションにおける信頼関係(ラポール)の重要性とともにご紹介しました。
- 【傾聴】相手がさらに話を続けやすくなるよう「真摯に聴く」
- 【リフレーミング】言葉の定義をリフレーミングする
- 【バックトラッキング】肯定感、そして信頼感を相手に与える話し方を心がける
- 【ペーシング・ミラーリング・マッチング】相手の仕草や表情、声色を観察し、合わせていく
- 【価値観に注目する】自分が本当に大切にしたいものに気づく
看護コミュニケーションに漠然とした不安を持っている方、さらなる看護コミュニケーションスキルを身につけたい方は、上記の手法を実践の場でぜひ試してみてください。
実践し続けていくと、自分のコミュニケーションの成果が、どんな反応で返ってくるのか楽しみになると思います。
ここまで来たら早速実践してみませんか。